意味知ってる ネット用語クイズ 実力の若林
新刊『発信型英語 類語使い分けマップ』上田一三(編著) 、333ページ、ベレ出版 (2015/2/23)、¥ 2,052「日本人が英語のスピーキングやライティングをする時に、一番厄介なのが文脈に合った類語の使い分けです。本書ではスピーキングや英作文をする際によく使われる、最も重要な類語のグループを約100(動詞・形容詞・名詞)取り上げ、その使い分けやニュアンスを学びます。」とある。本書は、動詞では「~系の動詞」として日本語のことばの多様な意味をまとめて英単語グループを分類し、違いを解説するというアプローチをとっている。たとえば、「わかる」系動詞の使い分けをマスターでは、understand, know, recognize, appreciate, identify, catch, figure outなどそれぞれの動詞が持つニュアンスや使われ方を説明している。日本語の「わかる」は、「分かれる→はっきり区別できる→理解できる」と変化したので、「区別できる」「見つける」『判断する』などの意味合いを含むので、英語のundrestandではそぐわないと解説している。文脈に沿った単語を使えることに参考になる書籍である。
運だけの春日「まぁ実は春日は運だけでここまで来たんですけどね!」実力の若林「いや本当に運だけならここまで来れてねぇよ」春日若林「「…………」」
実力の若林がトレンド入り!
「日本人が知らないニュアンスが一目でわかるイラスト」「超頻出の重要構文」「使える英語に変わるワンポイント」を1単語=見開き1ページにまとめ、1冊で頭のなかでホコリを被っている英語を活用できるようにしてあることが本書の売りである。例えば、 “earn”のコアイメージは、「努力の対価として、何かを手に入れる」ことで、He earned a bachelor’s degree at UCLA. He has earned the respect of his colleagues through his hard work. など、「稼ぐ」というイメージが日本人にはこびりついているが、お金以外の物に対して、努力によって手に入れるという意味を持っている。などの解説がある。挿絵もついて分かりやすい説明となっている。
新刊『特別授業3.11 君たちはどう生きるか (14歳の世渡り術)』あさの あつこ (著), 池澤 夏樹 (著), 鎌田 浩毅 (著), 最相 葉月 (著), 斎藤 環 (著), 橘木 俊詔 (著), 田中 優(著), 橋爪 大三郎 (著), 鷲田 清一 (著) 245ページ 河出書房新社 (2012/3/3) 1260円3.11で何が問われ、何を学び、どう生きるのか。これからを担う10代から20代に向けて、[国語]あさのあつこ、[歴史]池澤夏樹など、全9教科、紙上特別授業。豊富な注釈、資料データ入り。国語 「表現する力をつけてほしい」 あさのあつこ歴史 「きみは世界史の中にいる」 池澤夏樹倫理 「支えあうことの意味」鷲田清一地理 「日本とはどんな場所か? 今後どうなるのか?」 鎌田浩毅政治 「いまこそ政治の本当の意味がわかる」 橋爪大三郎理科 「科学は私の中にある」最相葉月経済 「経済成長より大切なこと」橘木俊詔保健 「いま、こころのケアとは?」 斎藤環課外授業 「『祈り』の先にあるもの」 田中優書店には3.11のコーナーが有り多数の書籍が並んでいる。本書はそのうちに一冊である。
新刊『13歳は二度あるか』(だいわ文庫)吉本隆明(著) 192ページ 大和書房 (2012/8/10) ¥ 6302005年に単行本と出版されたものの文庫版吉本ばななさんの父、吉本隆明氏は思想家で、今年3月に亡くなられた。新聞紙上では訃報を告げる記事が多数掲載された。本書は、「13歳は一度しかない」つまり、繰り返し得ない大切なときなのだ、というのが題名の意味であろう。表紙裏に、「先が見えないこの時代。世の中がひっくり返るような出来事がこれから起こらないとは限らない。大切なのは、今の時代の姿を自分で判断すること。社会との関わり方、宗教、国家、犯罪、戦争…。いま、何を見るのか、どう読むのか。"思想界の巨人"が語った、「現代」を生きるということ。」とある。中学生たちへ諭した生活上の心構えとして、新聞をよく読むことを挙げている。HRでの話にいかがですか。
旧刊『教育の方法―心理学を生かした指導のポイント』井上 知義ら(著) 174ページ 樹村房 (2007/11) 1995円「教育の方法」というタイトルの書籍には、佐藤学(著)『教育の方法』(放送大学叢書) 200ページ左右社(2010/7/30)などがあるが、私が気にいったのは、様々な教育方法を心理学を通して説明していることと、見開きの右のページに図解や表などを添付しより具体的なイメージを抱かせやすいようにしている編集スタイルである。「学習者の認知と情報処理」「学習者の認知を考えた教育の方法」「学習者の認知にあった教育の技術」「学習者の認知にあった教育の評価」の4章を扱っているが、現職教員にとってもreminderとして、教育の方法を再認知しておくことが、授業の活動に意味を持って行うことができると思う。
ツイッターで「実力の若林」がトレンド入りしている。若林と言えば、有名人だとオードリー若林を思い浮かべる人が多いだろう。したがって、オードリー若林が何らかの実力を発揮したのではないかと予想されるが、実力の若林の誕生秘話を見る限り、オードリー若林は無関係のようだ。
新刊『しぐさの日本文化』(講談社学術文庫)多田道太郎(著)、 272ページ、講談社 (2014/2/11)、 ¥966ふとしたしぐさ、身振り、姿勢―これらは個人の心理の内奥をのぞかせるものであると同時に、一つの社会に共有され、伝承される、文化でもある。身体に深くしみついた、人間関係をととのえるための精神・身体的表現といえる。あいづち、しゃがむ、といった、日本人の日常のしぐさをとりあげ、その文化的な意味をさぐる「しぐさ研究」の先駆的著作。初版は、筑摩書房から1972年7月に単行本として刊行されている。それが今年、講談社学術文庫として再版された。「しゃがむ」のエッセイには、「しゃがむというのは、どうにも格好のとれない姿勢であるらしい。トイレの中は別として、少なくとも公衆の面前でしゃがむのは不体裁この上も姿勢とされている。いわば文明によって禁圧されている姿勢、それがしゃがむ姿勢である」と冒頭にある。あのヤンキー座りも不体裁この上もない姿勢ということである。「文明は、人に立つか歩くか、それとも座るか寝るか、を命じている。しゃがむというのは、ネルでモナク、龍でモナク、その中間にあって京都弁でいう「アアシンド」に当たる身体表現であろう」と加えている。ヤンキー座りは、「アアシンド」と思っている座りかたのだろうか。トイレも今では様式がほとんど、駅や公園などでしか和式トイレを見かけることはない。Japanese Style ToiletというよりSquat Toilet と伝える方が分かりやすいと娘から聞いた。
旧刊『英作文なんかこわくない 日本語の発想でマスターする英文ライティング』猪野真理枝(著)、283ページ、東京外国語大学出版会 (2011/4/15) 1680円日本語は英語と非常に異なる言語構造を持つために、日本人が英作文をすると、日本語をそのまま直訳したような英文を書きがちである。本学の学生にもその傾向が顕著に現れる。思考の言語と表現の言語が異なる場合、両者を中継する言語知識が必要である。本書はその点に着目し、日本語の文法を正しく理解し、その意味に対応する英作文のしかたを学ぶ対照言語学的なアプローチで説明を試みている。本書は5つのステップから構成:〈Step 1からStep3〉文型、立場表現、時間表現などの日英語どちらにも存在する表現形式を比較しながら、英作文の練習をします。〈Step 4〉日本語にない構造である「無生物主語」と英語にない構造である「主題文」を知り、それらを英語で表現する方法を学びます。〈Step5〉日本語をより自然な英文にするために、日英語の「文の基本構造の違い」を知り、「自然な英文をつくる」ための総仕上げをします。
新刊『これならわかる、使える そうだったのか★英文法 (田中茂範先生のなるほど講義録1)』田中茂紀(著)、262ページ、コスモピア (2011/8/27)、1575円帯に「さまざまな英文法の疑問に、30年の研究が生んだ眼からウロコの明快答。」とあるが、NHK出版等からイメージ文法の書籍を多数出版されている田中氏の講義録整理版。・数えられないappleってどんなapple?・He is no father.とHe is not a father.とはどう違う?・There you are./ There you go./There it is. それぞれどんな意味?・Going, ging, gone!って何のこと?など、もやっとしたことをすっきりさせてくれる書籍である。
新刊『英文法の楽園 - 日本人の知らない105の秘密』(中公新書)里中 哲彦(著)、212ページ、中央公論新社 (2013/8/25)、777円I'm into English! Ditto!!と表紙帯にあるintoはtoよりも突入感を持つ語である。方向を表すtoはそこまで行ったなど野意味を持つが、中に入ったかどうかはわからない。内部への移動を表す突入の感覚を持っていることを頭に入れておくと分かりやすい。そうした、日本人が知らない、ネイティヴに通じる実践的な英文法を、Q&Aの形で楽しく学べるこの一冊である。通勤途中の頭の体操として読んでみるのはいかがだろう。豊富な例文がちりばめられた105の項目で英語のセンスが増すのではないだろうか。
【問題】「実力の若林」ってどんな意味?
「英語力=研究力、英語力=経済力、英語力=国際力という神話がまかり通っている」「外国からの留学生は英語による授業を望んでいない、日本の文化・考え方を学びたい」「アメリカを蝕む大学ランキング競争――なぜアメリカの大学教育は劣化しつつあるのか」など刺激的な論考である。鈴木孝夫氏の考えに同調されている寺島氏の主張は、ややもすると現状の英語教育改革の波に流されそうとする際に、自身が考える英語教育の展望と見通しを定かにし、進むべき方向の意味と価値を再確認するための灯台の光となるものである。様々な考えをしっかり認識し、生徒や学生への英語教育に望みたい。
新刊『一生モノの英語勉強法――「理系的」学習システムのすすめ 』(祥伝社新書312)鎌田裕毅、吉田明宏(著)、280ページ、祥伝社 (2013/3/2)、¥ 861「本書では、英語の学習そのものを「理系的」に解体して、効率的に上達するためのコツをわかりやすく提示します。つまずきの場所やステップアップの勘所をつかめば、一生モノの英語力を身につけることができるのです」を売りに英語の勉強法をあの人気京大教授が語っている。理系的学習法というのかどうかは別として、英語の勉強の仕方を著者の考えで整理している。The man made for the exit. これはどのような意味か?makeを作ると概念で縛っているとわからない。前置詞の意味合いとどう絡むのか、そうした構造的な理解も大切である。
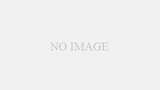
コメント