複雑化するアメリカ社会の分断 データからわかる意外な事実 マネーポストWEB
リスクマネジメントの要諦は、信頼できる正確な情報を収集し、これをもとに、リスクの発現する可能性とリスクの程度を正確に評価し(リスクアセスメント)、これに対する最適な対応策を分析し、実行に移すことにある。これには、直面する状況に対し、弾力的に対応できる力、すなわちレジリエンス(Resilience)が求められる。このようなリスクマネジメントの要諦は、どのような種類のリスクにも当てはまるものである。新型コロナウイルスの感染リスクに対して、レジリエンスを高め、リスクマネジメントを実践する機会と捉えることが、今後、自然災害や人災を含め、さまざまなリスクと共存できる社会を志向することにとって肝要であろう。
マネーポスト不動産売却|NEWSポストセブン|ダイエットポストセブン|介護ポストセブン|育毛研究室 by ポストセブンlab.|ウォーターサーバー研究室 by ポストセブンlab.|脱毛研究室 by ポストセブンlab.|WiMAX研究室 by ポストセブンlab.|転職研究室 by ポストセブンlab.
通勤・通学ラッシュの問題のように、個人では解決しにくく、社会で対応せべき問題が「政策問題」とされ、その政策問題の解決案が「公共政策」である。さらに、政策問題とその解決策である公共政策とを研究の対象とするのが公共政策学である。現代社会において社会問題はますます複雑になり、既存の学問では十分な解決策を提示できない、そうした意識から生まれたのは「公共政策学」、政治学や行政学、経済学など多分野の知識を総合化した新しい学問だ。専門家のみならず、市民の「知」も取り入れるなど、問題解決に役たつ学問へと進化しているようだ。公共政策学をどのように構築していくのか、それはより良い社会をつくっていくための公共政策の改善にもつながっていくのであると感じた。
今回、政策科学の授業においてソーシャルキャピタルという概念を学び、客観的な数字にはっきりと表れにくい「社会的つながり」を、数値化し研究対象とするための方策の一助を学んだ。客観性を得うるデータとして「社会的つながり」を学問の対象とすることは、まさに私が追い求めていた方策であり、私の今後の研究において非常に意義深いものとなるであろう。
この日本社会の特徴は、政治的意思決定を、いかに社会の実情に適合したものにしてゆくかを考える上で重要な意味を持っていると考えられます。なぜなら、日本社会の特徴と、現代政治における政策過程の複雑さに鑑みれば、政治的意思決定が国民の意思および社会の実情から乖離したものになってしまう可能性が増すことは明らかだからであります。いかに、より良い合意形成を実現してゆくかを考える上で、この抗議は大きな示唆を与えてくれたと感じております。
国際市場への進出は、必然のごとくその進出国の文化、政治、法律等に左右される高いリスクを伴うことを考慮に入れなければならないであろう。しかしながら、営利を目的として企業活動を遂行している以上、そのリスクを克服し、或いは、味方につけるような経営のマネジメントが要求されるのではと考えます。
第二に多様化の面です。インターネットを通じて色々な情報が手に入れられるようになった、というのは良く言われることですが、インターネットを通すことの出来る情報の質が多様化しているのが、この側面としてあげられます。音声のまま会話したり、或いはテレビ電話を実現したり、文字のみのメールを送ったり、データベースを用意したり……と、単にコミュニケーションを図ると行っても、その手段が、コンピュータという方法の内部でさらに分岐を起こすことで、より多様な可能性を産み出しているといえるでしょう。例えば、遠隔地において、医師が患者に簡単な診察を施すようなことは、技術の進化無しには不可能でした。
本学社会科学研究科では、「地球社会論」と「政策科学論」の二つに専攻が分かれている。筆者の専攻は前者の「地球社会論」である。一見すると、両者は切り離されているように見えるが、実は、両者は互いにリンクしており、その意味では分離することはできないだろう。むしろ、両者の学問的対話は深まるべきであり、そうすることによって、複雑かつ難解な諸問題に対する処方箋が出せるのである。
第一に、生命科学への期待である。スマートフォンを使った接触確認アプリが開発される一方で、個人情報の問題が指摘されている。このような葛藤は、データありきの情報科学の限界を突き付けている。未解明なCOVID-19に対して、生命科学がいまこそ求められている。ナノメートル・レベルの極小なウイルスの恐怖に対して、人はどのようにして安心を得ることができるのであろうか。世の中に安全基準はあるが、安心基準はないのである。
新型コロナウイルス感染拡大は、人の経済活動を支える行動様式に不可逆的な変化を与えている。すなわち、感染防止のためリモートワークやソーシャルディスタンスが推奨されるなど、人同士の物理的な接触を可能な限り回避する、新しい生活様式(ニューノーマル)が定着しつつある。緊急事態宣言が解除されても、目に見えないウイルスに感染するリスクに身をさらしながら日常生活を送らなければならないという状態は当面続くと見られる。この状況下では、個々が「リスクマネジメント」として新型コロナウイルスと向き合う意識で対応することが肝要である。自分は感染しないという「楽観バイアス」により感染対策を怠ることは、感染リスクの過小評価に基づく行動である。リスクマネジメントの観点からは、同じ感染予防の行動であっても、人の目や批判を恐れ、他人と同様の感染予防を行うという「同調圧力」による受動的な行動よりも、自己の置かれた状況を踏まえ、感染リスクを客観的に評価し、そのリスクを管理するための主体的な行動の方が望ましいと思われる。
この作業を続けていくとある一つの結論にたどりつきます。それは、世の中はすべて仮説の上に成り立っているということです。そして様々な仮説によって世の中の見え方が異なるということです。つまり世の中の見え方自体が、各人の頭の中にある仮説によって決まっているということに気付くことになります。その自分の頭の中に生まれてきた仮説を検証するために事実のデータを集めますが、そもそも頭の中にはその仮説によって決められた枠組みがあり、その中でデータを解釈することになります。だから、データをいくら積み重ねてみても既存の仮説を覆すことはできないことがわかります。要するにある理論を超えるのは、データの積み重ねではなく自分の頭の中で考えた仮説に基づいた理論だけということになります。この仮説はどうやら突然生まれてくるわけではなく、先達が積み上げ発展させてきた概念と理論的枠組みを根気強く現実社会に妥当するようです。そして後世が現実社会にアプローチする方法として引継がれていくようなレベルにしていくことに意義があるように思います。この連続性こそが学問の醍醐味であり、最高の状態で引継ぎ、また最高の状態で引き渡していくことが研究者の存在価値であると考える次第です。
COVID-19のパンデミックへの対応を振り返ると、感染症拡大抑制に関してだけでなく、行政、医療、働き方、教育など、さまざまな領域でICTの利活用に関する課題が見えてきた。特に、感染症拡大状況を把握するために、各保健所からのデータ収集にFAXが使われていたり、テレワークはできても、押印や請求書処理のために出勤する必要も生じた。また、街角での人の密集度などは、通信会社などのサービスからデータが収集されたが、住民へのフィードバックがされていない。また、特別定額給付金はオンライン申請しても、自治体側が手作業で住基ネットの住民データとの確認をしなければならないといった行政システムの準備不足も露呈した。
Society5.0構想は、「現代の石油」といわれるデジタルデータを活用して生活を向上させる社会の実現を目指してきたが、まさに、今回のように「移動」が不自由な状況で、「人間らしい生活」を送るためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)加速が欠かせないことに、気づいた人も多いだろう。
これは「市民によるメンバーシップ組織」から「専門家によるマネージメント組織」への変容、とも言い換えられるが、その背景にあるものとして、"コミュニケーションメディアの変化(テレビ・IT利用)"、"財源の変化(多数の会費から一部の高額な寄付)"のほか、"高学歴女性の役割の変化(地方における地域コミュニティの大黒柱的役割から都市中央部でのキャリア志向)"なども挙げられていて興味深い。
以上のことを自らの研究分野に引き付けて言い換えれば、「統計からはじき出されたデータや、頭の中で組み立てた理論だけでは、一人ひとりが置かれた状況や立場、信条等によって異なる多様な現実の意思決定の全てを把捉できない」ということになるのではないだろうか。つまり、地域に住む人々・ボランティア活動を行っている人々など、現実を築いている「人間」を対象として観察することなしに、現在起きている現象を捉えることはできない。研究を進めていく際には、一人ひとりの「人間」についての考察を総合化することで作られる、蓋然性を踏まえた多様な「現実」の流れを意識して考察を進めなければ、表出する結果・データの裏に隠れた事実を見逃がしかねない。このことは、研究を進めていく際に、常に認識しておかねばならない「戒め」となったように思う。
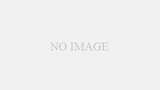
コメント